|
欧米人の考え方のバックボーンであるキリスト教においてワインは非常に重要な役割を担っている。最後の晩餐でキリストがワインを「我が血」と呼び表したのは顕著な例であろう。
特にフランスでは、ワインはただのアルコール飲料ではない。日本では「米」が日本食の文化の代表例に挙げられるが、ワインに対するフランス人の想いはその比ではない。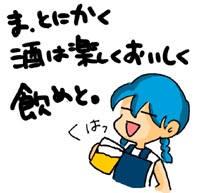
ワインは土地の誇りであり、文化でもある。フランスの魂そのものといっても良いかもしれない。
ありがたいことに、異教徒である我々もワインを味わうことによってその奥深い思いの一端に触れ、豊かな恵みを享受することが出来るのだ。
葡萄の表皮についた酵母によって葡萄果汁の発酵がはじまる。このようにして、人類が誕生する以前から自然現象としてのワインは存在していたであろう。
葡萄のあるところにはワインがあり、ワインがあるところには歓びがある。今日はブリタニアのワインについて一考してみたい。
と、えらく格調高く始まるわけだが、当然ブリタニアの気候。風土、葡萄などについては「えっとぉ〜、こんな感じぃ〜」でしか判らないわけである。しゃぁない、これはあくまで「こんな感じぃ」から判断されるブリタニア・ワインについての語りである、という事を先に述べておこう。うう。
 不味いワインの代表格--Britain-- 不味いワインの代表格--Britain--
ブリティンと言うからには気候風土はおそらく地球のブリティン島、イギリスに近いのであろう。イギリスにおいてはワイン用の葡萄栽培は盛んにはならなかった。しかしながら中世のイギリスがワインの供給には困らなかったのはフランス北部のノルマンディと、特に重要なワイン生産地である中部のボルドーをその版図としていたためだ。現在のようなボルドーのワインの隆盛は、当時のイギリスからの需要無くしてはありえないことであった。イギリスは自国内でワインを生産しなくても、十分消費をまかなうことが出来たのだ。
さてブリティン。
地球上のブリティン島と同じ気候である場合、まず緯度の高さが理由で、葡萄が十分育成するには日照量が足りない。必然的にそこで作られるワインは糖度が低く、タンニンの少ないものとなる。つまり「なんかすっぱくて薄くてボディが無い」不味いワインの代名詞となるのだ。
前項のGeographyにおいてブリティンが日本と同じ気候ではないかと妄想したが、その際も状況はさして変わらない。日本の雨量の多さはワイン用葡萄の育成には向かないのだ。水分が多い葡萄はみずみずしく生食用には非常にむいているが、ワインにするには水っぽくなりすぎ旨味が凝縮していないと判断される。更に発酵時にも腐敗が発生しやすい。現代の日本においてのワイン産業は生産者の努力の結果、水準をかなり上げてはきているが、数十年前までは「悲惨な状況である」の一言で済まされていたものである。そしてブリタニアの醸造技術は決して発達しているとは言いがたい。
いずれにせよ、ブリタニア、ブリティンのワインがさまざまな人々から酷評され、それしか飲む物が無い時には舌打ちされながら口に運ばれている事は予想に難しくはない。
野趣たっぷりワイン--Jhelom--
亜熱帯気候であろうジェロームでワインが生産されているなんて話、あまり聞いたことはないのだが。
しかし、気候から考えると現代のワイン生産、醸造技術をもって葡萄を作り始めたならば、現代人の舌に合う、「濃くて早飲みできるワイン」が出来そうな感じである。まぁ,ミクロ・ブラージュとかブリタニアで出来るはずがないので考えるだけ無駄無駄無駄なのだが。
それはともかく、ジェロームにおいてワイン醸造がされているとすると雰囲気としてはイタリア諸島部ワインが近そうなイメージである。色調、アルコール度は豊かで、雑味とまでも思えるような土や茎の香りの強さ、味わいは非常に濃厚。粗野な感じで苦手だという人も多いかもしれないが、飲みなれるとその味わいは土地の料理と非常にマッチして、こたえられない。多分。
また、この地では酒精強化ワインが主になるのかもしれない。
気温が高いため、ワインはすぐに熟成してしまい、そのままにしておくと発酵が更に進みワインはビネガーになってしまう。醸造中で発酵を止めるため途中でブランデーなどのアルコールを添加、アルコール度を20度前後までに高める。スペインのシェリーやポルトガルのポートワインなどが代表格である。途中で発酵を止めるため糖分が多く残り、甘くて(甘くないものもある)コクのあるものになる。
封を開けてからも保存が結構利くので、またり〜と飲むのに向いている。
憧憬の大地--Yew--
誰もが賛美してやまない、ユーのワイン。果たしてどのようなワインなのであろうか。
前回のGeographyでは「ドイツのような気候かも」と書いたわけだが、ユーのワイン、と聞いた時に思い浮かぶ味わいはなんとなくドイツのものではない。だってユーのワインったら赤じゃん。ドイツでは近年、赤ワインの生産量が少しずつ増えてきているとは言っても全体の25%を占めるにとどまっている。
それでは、ユーのワインはどのようなものなのであろうか。
ここでイメージを膨らませてみる。ユーと言えばエンパス・アベイ(Empath Abbey)、修道院である。修道院とワインと言えば切り離す事のできない、深い関係にある。そういえばシャンパンを発見したのも修道士ドン・ペリニヨン師であった。中世、土地持ちは修道院にどんどこ土地を寄進した。代表的な例がオスピス・ド・ボーヌである。オスピス・ド・ボーヌと言えばブルゴーニュ。
おお、ブルゴーニュっ。
フランスではボルドーと双璧をなす大銘醸地で、かの有名なロマネ・コンティも輩出する偉大な土地。
というわけで、筆者の頭の中では即座にユー=ブルゴーニュという事に決定してしまったのであった。なんと強引な。
気候、土地、水、そして人間、全ての要因を総括して「テロワール」と呼び習わすのだが、ブルゴーニュ=ユーのワインはそれを見事なまでに体現する。奇跡的なまでの大地の恩恵、信仰に近い愛情を葡萄に注ぐ人間、そして人を時には希望に打ち震わせ、時には絶望の淵に叩き込むその年その年の気まぐれな天候。それらすべてからピノ・ノワールの華やかかつ繊細な香り、シャルドネの芳醇な味わいが生まれだす。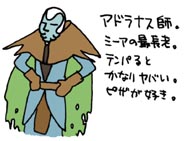
近年、恐怖の天然ボケ、永遠なる監視人アドラナス氏の魔法の失敗によりトラメル・ユーの大地が腐敗し、葡萄の生産が極度に落ち込んでいた。
あの豊饒の大地を腐敗させるとは・・・か、神をも恐れぬ所業である。
ようやくユーが腐敗から立ち直り、大地は再び息づき始めた。しかし、樹齢を重ねた葡萄の幹の多くは長年の腐敗によって息絶えてしまっているであろう。しかし、おそらくはワインを愛するユーの生産者たちの手によって、いつか再びすばらしいワインが作り出され始める事を心から信じている。
夢見たものは・・・--Trinsic--
美しい外壁に周囲を取り囲まれたトリンシック。気候は温暖でインフラも整っている。首都ブリティンからの距離も程よく、重要な都市のひとつである。しかし、土地の生産性、および戦略的に重要な地点であるがゆえに何度も外敵からの襲撃を受けてきた、悲劇の街なのだ。
トリンシックの地形、気候を考えると、それは非常に葡萄の生産に適しているように思われる。おそらく、質、収穫量、共に非常に高いものになるであろう。
しかし。
トリンシックと言えばオレンジ、誰がなんと言おうとオレンジなのだ、筆者はジョン・フェルナンド氏の「オレたちゃUO人間」の、「オレンジ」のファンなのだ(フラッシュ見てない方は
ぜひご覧になってください)。
夢に見るのは、大地が金色に輝き、人はみな、楽しげに笑いを浮かべながら帰宅の途につくオレンジ色のあの頃・・・あう、ロマンだ。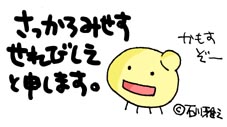
しかしながら。じゃぁオレンジでフルーツ・ワインを作れば、という事になるかもしれないが、実はオレンジ・ワインはあまり存在しない。長年、どうしてオレンジなどの柑橘系のワインが無いのか疑問に思っていたのだが、「もやしもん」によると柑橘系は青カビと仲が良すぎるらしい。おそらくは青かびが酵母菌を圧倒してしまうため、醸しに入れないのであろう。(ここら辺、文献未確認の為、情報求む)
オレンジの酒となると、アルコールにオレンジ果汁を入れた物という事になる。赤ワインにオレンジ果汁を入れたサングリア、蒸留酒とオレンジの果皮で作るオレンジ・リキュールなどがトリンシック・オレンジでの酒類という事になるのではなかろうか。
追記。ジョン・フェルナンド氏によれば、トリンシックはスペインを想定されているそうな。なるほど、すごく納得である。
スペインといえば思い出されるひとつの寓話がある。
神様がスペインを旅された時、その土地でのもてなしに感謝をされ、願いをいくつか聞き届けることを約束した。民は言った。「いつでもすばらしい収穫が約束されるよい土地と気候をください」神様はうなずかれた。さらに民は言った。「明るくていつでも笑顔がある、すばらしい人たちをここに住まわせてください」再び神様はうなずかれた。さらに民はいった。「すばらしい政治もください。」すると神様はこう言われた。「すばらしい土地とすばらしい人民だけで、もうお願いはたくさん過ぎです。」というわけで、この地にはずっと、よい政治は無いのであった。
明るい太陽と青い空、広がる大地と深い思い。スペインにもトリンシックにも、溢れる情熱が似合うのであった。
謎すぎる、あまりに謎すぎるワイン--Heartwood--
「君たちにエルフ式吟醸法を教えてあげよう」
NPCエルフってなんでこうもタカビーなのだろう、伝統的にエルフがタカビーになったのはやはり指輪物語以降の事なのだろうが。
このエルフ式醸造法というのが今のところどのようなものなのか一切明かされていない。教えてあげると言ったんだから教えておくれよ、あんなに頼みごとを何度も何度も聞いたのに。
ところで、ひとつ注目したいのは多くの人が宝珠導入の際に鬼のような勢いでやりまくったであろうクエスト。エルフNPCは何と言って用事を頼んだ?
「我々エルフはヒューマンのワインと我らのワインを交換したいと考えているのだが、ヒューマンはこうした液体を奇妙な入れ物で運ぶと聞いた。ガラス瓶というやつを、何本か揃えてくれないか?」
なんとエルフは瓶を知らなかったのだ。ワインの歴史を考える上でガラス瓶の存在は非常に大きいものである。ワインをガラス瓶につめ、そしてコルクで栓をすることにより保存、運搬の利便性が格段に向上したことはもちろん、瓶内熟成によるワインの品質の向上が果たされたのだ。こ、こいつらのワインってもしかして超早飲みなのか?
更には「考えられん!なぜヒューマンたちは、大切なワインを木の棺桶などに詰め込んでおくのかね?このいまいましい木の入れ物から黄金の液体を取り出すには“注ぎ口”が必要なのではないか?それを持ってきてくれたなら、共にワインを分かちつつ、エルフ式ワインについて教えることができるのだが。」
う。木樽でも無いのか、エルフのワイン。まさかして、ステンレス樽・・・
謎すぎる、あまりに謎すぎるエルフのワイン。さすがはエルフ、今までヒューマンが口にしたことのないビビッドでファンタスティックな味わいを見せてくれるのであろう。
奇跡の味--Skara Brae--
本家ウルティマ6では「スカラブレイがワインの産地として有名」だという情報を入手した。その情報によると、スカラブレイは港町としてにぎわっているが、桟橋を渡るとそこには畑と広大な森が広がっている。よくウイスプが出現することからその森は崇高なものと考えられ、そのためにスカラブレイの街は崇高な精神の中心地、とされたのだという。スカラブレイの人々が崇高であるわけではなく、ただ、スカラブレイ産のワインを飲む時に崇高さを感じているに違いない、との辛口コメント付きであった。さすがはウルティマ。
港街、そして最高峰の味わいのワイン、となるとスカラブレイ・ワインのイメージは一つしかない。
ボルドーである。
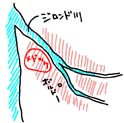
中世、イギリスの版図にあったボルドーは、イギリスにおいて非常にメジャーな存在である。現在のボルドー・ワインの隆盛はイギリスあってのものだ。ジロンド川の河口に開けたボルドーは貿易港として大いに栄え、偉大なるボルドー産のワインをイギリスの食卓に届けていった。
一つしかない、とかいいつつもなんとなく納得できなかった筆者。
ボルドーか。確かにボルドーの近辺にはフランス最大規模の森が広がっているが、スカラブレイとボルドー・・・。干拓され、整然と美しい葡萄畑が広がるボルドーとスカラブレイのイメージはあまり結びつかないかもな、河口で港街、といってもスカラブレイは河口ってより出島じゃねぇか。
しかし。
川はボルドーの華麗なワインを作り上げる葡萄の育成に大きな影響を与えている。川の近くだからこその気候、堆積物、そのひとつひとつが奇跡のようにボルドーのテロワールを作り上げている。
そして、川はこの地方に霧をもたらす。
ボルドーのソーテルヌ地区では、霧による湿気が葡萄の表皮に菌の繁殖を促す。白い菌糸に覆われたセミヨン種の葡萄は、一見とてもではないが食べ物には見えない。どうみても腐っている。食えん。本能が無理だって言っている。そんなもん食いもんじゃねぇ。
しかし、腐った(をぃ)葡萄から「貴腐ワイン」という極上のデザートワインが作られるのだ。
葡萄の表皮を覆った菌糸(ボトリティス・シネレア菌)は表皮に穴を開ける。葡萄の内部からその穴を通して水分が蒸発、次第に葡萄の糖度は上がっていく。ほぼ干し葡萄状態になったその葡萄を使ってワインを作ると、非常に糖度が高い甘口ワインが出来上がる。
自然が作り上げた奇跡のようなワインなのだ。
緑覆う森を漂う、奇跡をもたらす霧。その不思議な霧の中にウイスプがふよふよと浮かんでいるのを想像してしまったら、妙にハマる物を感じてしまった。スカラブレイの森に霧が立ち込め、ウイスプは現われては消える。う〜む、神秘チックだ。きっとスカラブレイには霧が出るんだ。きっとそうなんだ。
ということで、筆者の中ではスカラブレイのワインはボルドー・ワインという事に決定してしまったのだ。相変わらず強引な気がおもいっきりするが。
ワインの世界は奥深い。食の世界は奥深い。ブリタニアの一料理人として、ブリタニアの食の世界について、更に深く考察していかねばならないと心に誓うのであった。
・・・こんだけ書いておいてなんですが、普段飲むならワインよりもビールです。
|